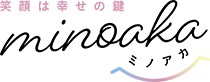「うちの子、歯並びが悪いかも。」
「子どものうちに矯正したほうが良いの?」
「矯正治療を始めるとしたら何歳からが良いの?」
お子さまの歯並びが気になる一方で、小さなうちから矯正を始めて大丈夫なのかと不安に思う親御さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、お子さまの歯並びが気になっている方に向けて、小児矯正を始める時期の目安やメリット・デメリット、装置の種類、費用についてお伝えします。
整った歯並びはお子さまの自信につながるだけでなく、全身の健康にも良い影響を与えます。
小児矯正で行うあごの成長を利用した治療は幼い頃にしかできないため、時期を逃さないためにも、子どもの矯正について事前に知っておきましょう。
小児矯正を始める時期と治療目的
小児矯正には「1期治療」と「2期治療」の2つの段階があります。
それぞれ治療内容は異なり、1期治療ではあごの形やバランスを整えて、2期治療では歯を動かしてきれいに並べる治療が行われます。
どちらか一方の治療を選択するのではなく、子どもの成長に合わせてトータルで考えるのが小児矯正では重要です。
ここでは、1期治療と2期治療それぞれの治療開始時期や治療の目的についてお伝えします。
1期治療(5~12歳)
1期治療は5歳頃から12歳までの子どもが対象で、まだ大人の歯(永久歯)が生えていない時期や乳歯と永久歯が混在している時期に行われる治療です。
治療の開始時期は歯の状態や歯科医院の方針によって異なりますが、5〜8歳頃から開始し、治療期間は2〜4年ほどです。
歯並びが悪くなる原因の多くは、あごの成長不足にあります。
あごが未発達のまま歯が生え変わると、乳歯よりも大きい永久歯の並ぶスペースが確保できず、歯並びがガタガタになってしまいます。
1期治療の目的は、これから生えてくる永久歯がきれいに並ぶように、あごの成長をコントロールし、歯の生え変わりを正しい方向へ導くことです。
2期治療(12歳以降)
2期治療は永久歯が生え揃った12歳以降に行い、治療期間は1〜3年が目安です。
15歳以上になるとあごの成長が終わるため、成人矯正と同じようにワイヤーやマウスピースを使用して歯を動かす治療が行われます。
1期治療では改善できなかった、細かな歯並びのズレを調整することが可能です。
あごの成長に問題がない場合は、1期治療は行わず2期治療から始めるケースもあります。
矯正歯科へ行くタイミング
お子さまに矯正を受けさせるべきか判断に迷う場合は、小学校入学前の5歳頃に矯正歯科で相談することをおすすめします。
一見きれいに歯が並んでいても、矯正治療を行うのが望ましいケースも少なくありません。
例えば、ディープバイトと呼ばれるかみ合わせが深い状態は、奥歯に強い負担がかかっているため、歳を重ねると歯を喪失してしまう可能性があります。
お子さまが将来「もっと早く矯正治療をしておけばよかった」と後悔しないためにも、歯が生え変わる前の5歳頃に一度矯正専門の歯科医師に歯並びを診てもらいましょう。
早期に矯正を始めるメリット
子どもが小さなうちから小児矯正を始めるメリットは、以下の5つです。
- 抜歯など回避できる可能性がある
- 永久歯の生え方を調整できる
- 大人と比べて装置の順応性が高い
- 顔のバランスを整えられる
- 口呼吸を改善できる
1期治療から始めればすんなりと歯並びが整うケースもあるので、メリットを知った上で治療するか判断するとよいでしょう。
抜歯など回避できる可能性がある
1期治療から始めた場合、骨格からアプローチしてあごを広げることができるため、将来、矯正による抜歯や手術を回避できる可能性があります。
一方で成人矯正から治療を始めた場合、あごが成長しきっているため歯のスペースを広げることができません。そのため、抜歯やあごの骨を切る外科手術が必要になる場合があります。
ただし、1期治療から始めても抜歯や手術が必要になるケースもあるので留意しておきましょう。
永久歯の生え方を調整できる
永久歯が生え揃っていない1期治療では、乳歯の抜けるタイミングをコントロールして永久歯の生え方を調整することが可能です。
乳歯が抜けて同じ場所から永久歯が生えてくれば問題ありませんが、乳歯が残ったまま違う角度から永久歯が生えてくるケースも少なくありません。
あごが小さいと歯が並ぶスペースがなくなり、永久歯が重なり合ってしまいます。
乳歯が残る1期治療では、乳歯を抜くタイミングを調節し、永久歯の生え方を正しい方向へ導くことが可能です。
うまくいけば1期治療のみで矯正を終えられるケースもあり、治療期間を短縮できる可能性があります。
大人と比べて装置の順応性が高い
個人差はありますが、子どもは大人に比べて順応性が高いため、矯正装置に早く慣れることができます。
歯の生え変わり時期である子どもの歯列は、刻一刻と変化するため、矯正による違和感とあごの自然な成長が重なり、身体が適応しやすいからです。
矯正への順応性が高ければ、矯正装置によるストレスを最小限に抑えることができるでしょう。
顔のバランスを整えられる
小児矯正を受けると顔のバランスを整えることができます。
かみ合わせの悪い状態を放置してしまうと、あごの成長に偏りが出てしまい、将来顔にゆがみが生じる可能性があります。
子どものうちに骨格のズレを正しい位置に戻すことで、顔のゆがみを改善することが可能です。
口呼吸を改善できる
口呼吸はあらゆる全身トラブルを引き起こす原因となるため、早期の改善が必要です。
小児矯正でかみ合わせを治療すると、口呼吸を改善することができます。
口呼吸を放置していると、細菌が口内から侵入しやすくなるため、風邪を引きやすくなります。また、口内が乾燥して唾液が行き渡らず虫歯のリスクも高まります。
舌の位置が下がって発音や顔貌にも影響が出るので、口呼吸は幼いうちに治すのが望ましいでしょう。
早期に矯正を始めるデメリット
早期から小児矯正を始めるデメリットは、以下の3つです。
- 治療期間が長引く可能性がある
- 虫歯のリスクが高まる
- 子どもの協力が必要になる
矯正治療はメリットが多い反面、お子さま自身が治療を負担に感じるケースもあるので注意が必要です。
治療期間が長引く可能性がある
歯並びによっては、あごの成長が完了する15歳頃まで経過観察が必要になります。
そのため、1期治療から始めてトータルで10年ほど通院が必要になる可能性があります。
虫歯のリスクが高まる
固定式の矯正装置を付けている場合、通常よりも丁寧に歯を磨かないと虫歯のリスクが高まります。
乳歯は永久歯と比べて柔らかく、虫歯の進行が早いため毎日のケアが重要です。
矯正中は磨き残しが多くなりやすいので、仕上げ磨きをしてあげましょう。
子どもの協力が必要になる
小児矯正の治療の成功には子どもの協力が欠かせません。
取り外し可能な装置を使用する場合、子どもが嫌がり勝手に装置を外してしまうと治療で良い結果を得られない可能性があります。
治療を開始する前に、お子さまに治療の目的をしっかりと伝えて、同意を得ることが大切です。
【時期別】矯正装置の種類
小児矯正の装置は多種多様で、お子さまの歯並びやかみ合わせの状態に応じて使い分けます。
ここでは、時期別によく使用される装置の種類と特徴をまとめました。
1期治療で使用する装置の種類
1期治療で主に使用される装置は以下の4種類です。
特徴と併せて説明します。
| 床矯正(しょうきょうせい)装置 | ・歯列の幅を広げて歯を並べるスペースを作る ・レジン製のプレートに歯に装着するための金属が付いている ・取り外し可能 ・デコボコの度合いがひどい場合は使用できない |
|
|---|---|---|
| 急速拡大装置 | ・あごを広げて短期間で歯を並べるスペースを作る ・歯に装着するための金属製のリングとワイヤーが付いている ・上あごのみに使用可 ・固定式 ・装着直後や食事中は違和感がある |
|
| リンガルアーチ | ・歯列を外側に押し出して動かすことができる ・歯の裏側に沿ったアーチ状のワイヤーに奥歯に固定するための金属のリングが付いている ・固定式 |
|
| マウスピース型装置 | ・歯を動かすだけでなく口呼吸や舌の癖を改善できる ・プラスチック製やシリコン製のものがある ・就寝中のみ装着するタイプがある ・痛みが少なく負担にならない ・取り外し可能 |
|
歯の状態や担当医の考えによって、使用する装置は異なります。
2期治療で使用する装置の種類
2期治療で主に使用される装置は以下の3種類です。
特徴と併せて説明します。
| マルチブラケット装置(表側) | ・歯にブラケット(小さな突起物)を装着しワイヤーを引っかけて歯を動かす ・さまざまな症例に対応できる ・目立ちにくい透明や白色の装置がある ・メタルブラケットは目立つ ・虫歯のリスクがある ・装置が口内に接触し痛みが出る場合がある |
|
|---|---|---|
| マルチブラケット装置(裏側) | ・ブラケットを歯の裏側に装着してワイヤーを引っ掛けて歯を動かす ・目立たない ・舌に装着が当たり痛みが出る場合がある ・発音障害が出る恐れがある |
|
| マウスピース型装置 | ・1~2週間ごとにマウスピースを交換して歯列を整える ・ワイヤーを使用した矯正よりも痛みが少ない ・食事中はマウスピースを外す必要がある ・装着時間を管理しなければならない |
|
2期治療では成人矯正と同じ装置を使用します。
すでに1期治療を終えて歯の土台が整っていると、2期治療から始めるよりも短期間で治療が完了する可能性があります。
小児矯正の治療にかかる費用
矯正治療にかかる費用には以下のような項目があります。
- 初回相談料
- 精密検査費
- 抜歯費用(必要に応じて)
- 装置代
- 調整料
- 保定装置代
- 観察料
これらを全て含めると、1期治療はトータルで10〜40万円ほど、2期治療も行う場合は1期治療と合わせて80〜120万ほどの費用が発生します。
一般的な矯正治療は自費治療のため、病院や地域によって金額に差があります。
治療費用の詳細は矯正歯科に来院し、見積もりを出してもらいましょう。
まとめ
お子さまに矯正を受けさせるべきか迷っているなら、小学校入学前に一度矯正歯科で診てもらうことをおすすめします。
矯正の専門医がお子さまの歯並びに適した治療時期を提案してくれるでしょう。
幼い頃からの矯正治療は治療期間が長引くなどのデメリットもありますが、それ以上に得られることが沢山あります。
あごの成長を正しい方向へ導くことで、歯列が整うだけでなく、顔のバランスや口呼吸の改善にもつながります。
お子さまの健やかな成長のためにも、早いうちから小児矯正を検討してみてはいかがでしょうか。